
このページは「週刊読書人」に掲載された書評記事です。同社許可のもとに転載しています。(初出)「週刊読書人」2013年8月30日号6面(バックナンバーを購入)
ハーバード大学で日本近代史を研究するアンドルー・ゴードンの Fabricating Consumers: The Sewing Machine in Modern Japan (2011年)の邦訳版である。20世紀初頭から戦後にいたるミシン販売・購入・利用を追及している。邦訳はハンナ・アーレント等の訳書が多い大島かおりが行なった。
内容構成は、序論、第1部「日本におけるシンガー」(明治期のミシン、アメリカ式販売法、近代的生活を販売し消費する、ヤンキー資本主義に抵抗する)、第2部「近代性を縫う 戦時と平和時」(銃後の兵器、機械製の不死鳥、ドレスメーカーの国)、結論である。図版は本文の叙述を端的に示しており、内外雑誌広告やシンガー社広告から選ばれた絵や写真が40点近く収められている。また、索引が充実している。
まず、内容構成は以下の通りである。第1部は日本へのシンガー・ミシンの普及を扱う。前史として19世紀後半の普及から起こし(第1章)、月賦販売による家庭への普及(第2章)、近代に良妻賢母像が形成されていく中で女性自身が積極的にミシンを学び活用した経緯(第3章)、1930年代以降に生じたシンガー販売店のストライキや国産ミシンの台頭(第4章)を述べている。第2部は戦中・戦後のミシンと女性との関係である。国産ミシンの普及と、標準服・国民服の制定による和洋折衷化(第5章)、50年代、国産メーカーとシンガー社の競争激化と、女性洋服化の加速(第6章)、専業主婦像が人気を持つ中、商業生産か否かを問わず女性たちが裁縫学校へ殺到したこと(第7章)という流れである。
次に、本書の立場であるが、筆者はミシンを「消費者の欲望の対象であるとともに、生産財でもあって、家族のための衣類ばかりでなく、隣人に売る服づくりにも、内職の賃仕事にも使われた」(本書3頁)と述べている。その上で焦点を「工場よりも自宅での使用者に絞ってある」(7頁)とした。
近代日本の衣服生産は(1)生産場所は工場と家に、(2)家内生産は家族向けの家事労働と商業目的の家内労働(内職)に、(3)家内労働は開業型・隣人向け・部分縫製型に、それぞれ区分される。本書では(1)は家、(2)は両方、(3)は開業型・隣人向けが注目されている。消費財一辺倒に考えられがちなミシンを生産財の側面からも捉えた点は的確である。それゆえ、ミシン活用に関する叙述の幅が広がり、家事労働の延長から隣人向け生産が注目され、他方、洋服店を開業した事例や仲介人からの内職に従事した事例にも広く言及されている。
本書に最も共感したのは、和洋の二項対立に疑問を呈している点である。洋裁とミシン、和裁と手縫い、洋服と近代、和服と伝統、これらはセットで思われがちであるが、本書はこれらの境界に疑問を呈し、日本性と近代合理性との共存・融合を指摘している(特に123~124頁)。
最後に、興味深いことに、シンガー社の世界展開をグローバル化、日本でのミシンの普及と利用の実像、及び同社販売員の抵抗や国産ミシンの台頭をローカル化(変奏、333頁)として近代化・西洋化が議論されている(特に結論)。ただし、筆者が距離を置こうとするグローバル化の完全浸透という論点に対し、本書の主張がどの程度異なるかは判断が難しい。この点だけ言い添えておく。
(初出)「週刊読書人」2013年8月30日号6面(バックナンバーを購入)
アンドルー・ゴードン『ミシンと日本の近代―消費者の創出―』大島かおり訳、みすず書房、2013年
[amazonjs asin=”4622077701″ locale=”JP” title=”ミシンと日本の近代―― 消費者の創出”]




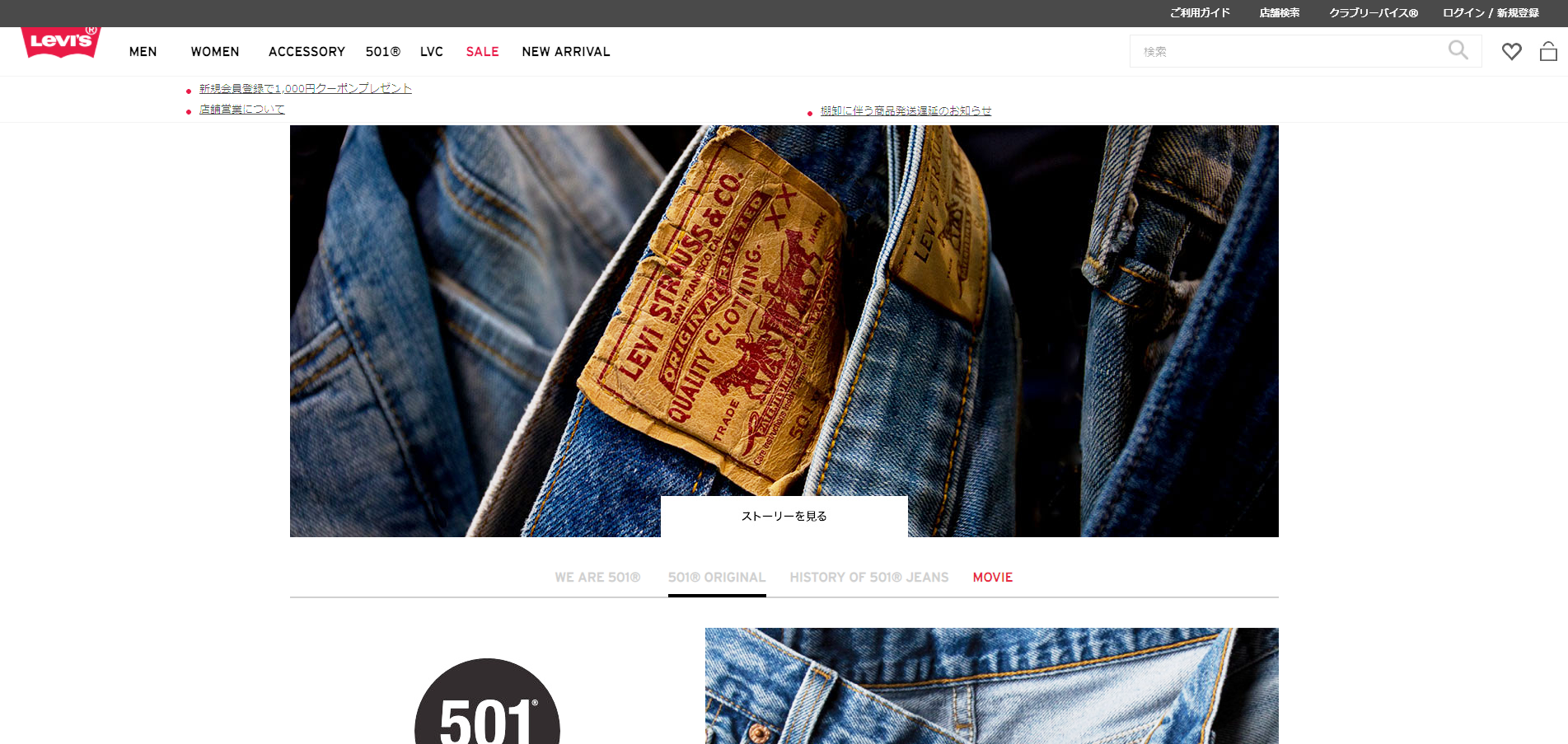
レビュー 作品の感想や女優への思い