このページは「週刊読書人」に掲載された書評記事です。同社許可のもとに転載しています。(初出)「週刊読書人」2016年12月9日号、6面(バックナンバーを購入)

台湾少女、洋裁に出会う
聞き書きと写真を交えて描く母の洋裁人生
少女から大人へ、そこにはいつもミシンがあった
本書の内容 : 著者の母の洋裁人生
本書は「台湾人女性が洋裁と出会い、そして別れるまでのドキュメンタリー」(26頁)である。その女性とは著者の母、施伝月(1918-2009)である。豊富な写真には訳者提供のものもある(211頁)。
施伝月は台南(Tainan)の蕃薯港に生まれた。話の中心地となる台南は、古くからの先住民族(シラヤ族)、植民地経営を行なったオランダ人、清朝期の移民(漢民族)によって栄えた街である。シラヤ族は現台南市安平区方面を大員(Tayuan)と呼び、これが台湾(Taiwan)の語源となった(訳者「はじめに」)。なお、台湾では1910年代から米国シンガー社製ミシンが普及し、それを担ったのが在台日系販売店であった(拙著『ミシンと衣服の経済史』思文閣出版、2014)。
彼女の洋裁人生は、幼い頃に手伝っていた家業の日用品店に始まる。店では商品を紙袋に入れて客へ渡していた。その紙袋は、当時日本で刊行されていた婦人雑誌類の古紙面を貼り合わせたもので、「そのなかに、洋裁のページがあった」(56頁)。
彼女は、洋裁見習いを希望するも家族から許されず、代わりに手廻式ミシンを買ってもらう。それには日本語の解説が付いており、ミシンだけでなく日本語も独習した。やがて妹や弟の簡単な洋服を作れるようになり、19歳の1936年5月、末広町にあった日系洋装店日吉屋に就職する。足踏式ミシンの経験がなかったが、直線縫で済む布団カバーを担当し、練習にはちょうど良かったという。
日吉屋を退職した翌40年に伝月は東京の東京洋裁技芸学院へ留学する。コースはデザインを勉強する裁断科で、規定年数は1年であったが、台湾で蓄積したミシン技術が評価された上、午前と午後の両コースに通ったため半年間で修了した。41年初夏に台南へ戻り瑞恵洋裁店を開く。
戦後台湾の洋裁ブームに拍車がかかるのは1970年頃で、既製服(レディ・メイド)の輸出拡大が主因である。90年代には逆に既製服輸入拡大により産業が縮小し、洋裁学校の人気は鈍化した。同じ頃、伝月の開校した洋裁学校「東洋裁縫学院」も閉校し、本書の物語は終わる。
日本帝国の統治、日中戦争・太平洋戦争下の貧困、戦争末期米軍の空爆、国民党の統治、70年代初頭の国連脱退とニクソン訪中。目まぐるしく変わる政治・軍事情勢のなかで伝月の辿った洋裁人生は淀まず、苦楽が活写されている。本書は個人史に留まらず東アジアの洋裁受容史としても貴重で、描かれる風景は日本の読者にも見覚えがあるだろう。
(初出)「週刊読書人」2016年12月9日号、6面(バックナンバーを購入)
鄭鴻生著『台湾少女、洋裁に出会う―母とミシンの60年―』 天野健太郎訳、紀伊國屋書店、2016年




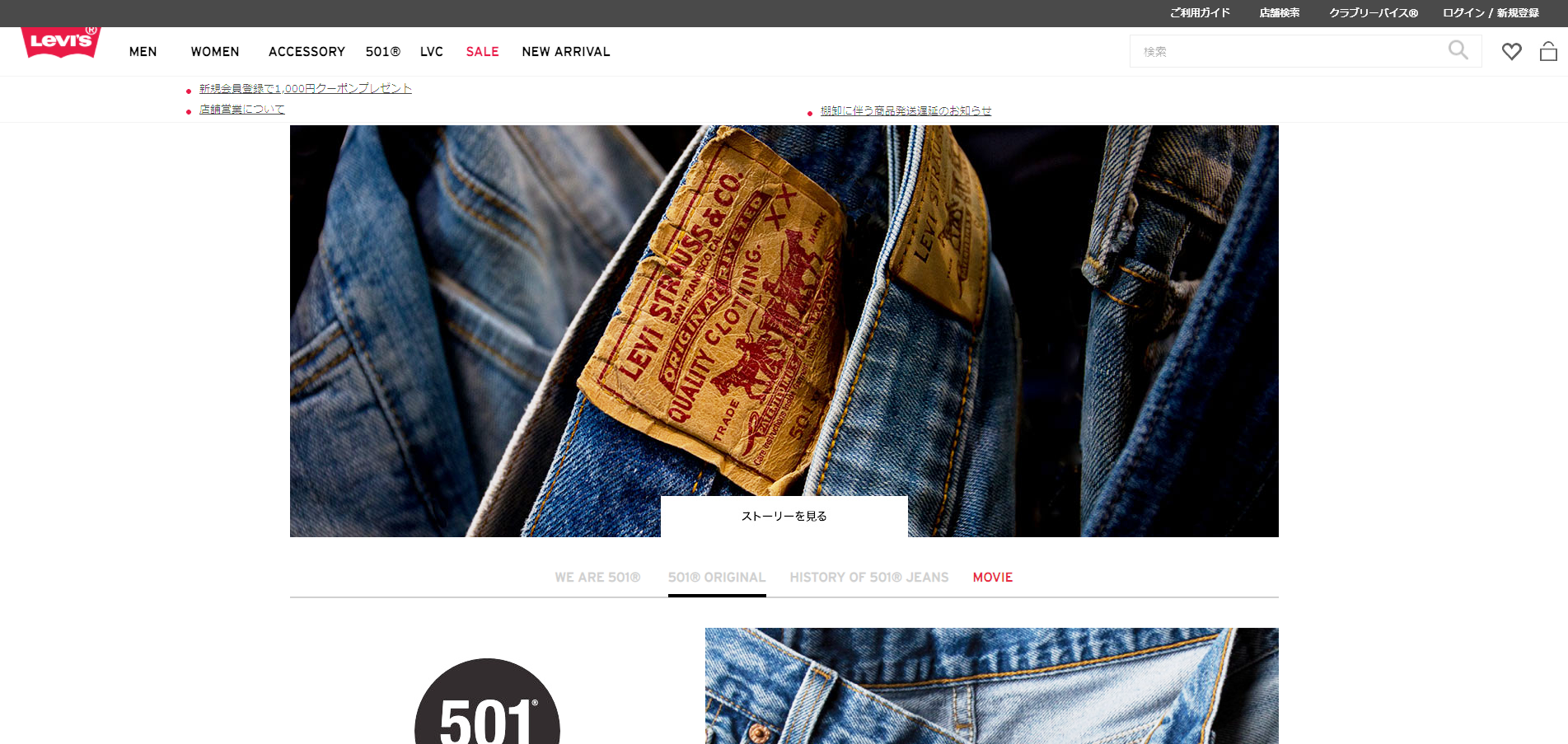
レビュー 作品の感想や女優への思い