オート・クチュール(haute couture)はフランス語で、日本語では「高級仕立店」や「高級衣料品」の意。オートクチュールと「・」を外して用いることが大半です。
狭義には「La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne」(パリ・クチュール組合、パリ高級衣裳店組合ともいい、通称サンディカ、サンジカ)に加盟し、組合規定の規模や条件を備えて運営されていた企業・店舗をさします。
1960年代頃から参加企業のプレタ・ポルテ化(既製服化)とライセンス販売が進み、また、製造工程の秘匿ゆえに「どの程度に高級か」が不分明のままで知名度が下がり、赤字経営も続いています。
既製服化とライセンス販売は、しばしば揶揄されてきました。1960年代にピエール・カルダンは「トイレにもカルダン」といわれ、1990年代にルイ・ヴィトンは「小学生もルイ・ヴィトン」と言われていました。
語源
オート・クチュールの語源は、16世紀に「グランド・クチュール」とよばれていた大衣裳店に「高級品」の意を表す「haute」をつけたことに寄ります。
当時の仕立業組織が「フランス・クチュール組合」を設立し、これが今日の「オート・クチュール組合」の原型となりました。
この組合は1947年に発令されたフランス政府の助成策によって特別の認定を受けており、パリ・モードの総元締として機能してきました。この組合に加盟していたメゾンは多い時で23を数え、シャネル、サンローラン、ディオール、カルダン、ウンガロ、ランバン、モリなどがありました。
所属企業の特徴
オート・クチュール企業は、テイラーやドレス・メイカーが顧客のためにオリジナルな衣装をデザインし、生地、仕立も含め最高級の完成度をもっているといわれてきました。そのため価格が非常に高く、顧客は上流階級に限定されてきました。
パリ・クチュール組合は、1月(春夏シーズン)と7月(秋冬シーズン)にコレクション(作品発表)を開催。その源流はシャルル・フレデリック・ウォルトで、19世紀の成立から20世紀半ば頃まで、世界中の上流階級の個人(おもに婦人)を顧客としてオーダー・メイドの服飾を作っていました。
19世紀末のオート・クチュールの局所的流行をみて、ヴァルター・ベンヤミンは、ファッション・デザイナーが画家かの勢いで衣料品に名前を付けたがるようになったと揶揄しています〔ヴァルター・ベンヤミン のモード : オート・クチュールの誕生〕。

シャルル・フレデリック・ウォルトのオート・クチュールのアトリエでブラウスをドレーピング中の写真。1907年、パリ。 via The draping of blouses in the haute couture atelier of Charles Frederick Worth. Paris, 1907. © Jacques Boyer / Roger-Viollet.
ただし、それらが全てミシン縫製を使わずに手縫いで行なっているという先入観は今でも根強いです。
たとえばウィキペディア日本版には「お針子が一刺し一刺し手縫いをして完成させる。ミシンは使わない。刺繍もレースもみな手編みである」と記されています(オートクチュール – Wikipedia)。「刺繍もレースもみな手編みである」と、縫製の話から編物の話に突然移行している点も怪しい記述になっています(手縫いの間違いでしょうか)。
所属企業の多角化
戦後の世界情勢の変化を大きな背景にして、顧客の大富豪が減少したことや働く女性が増加したことなどにより、ファッションの傾向が既製服へと転換。
1960年代以降は、複製権を販売したり(ライセンス契約)、プレタ・ポルテ部門をもったり、香水・スカーフ・下着などを販売したり、グリフ(クチュールの店名)の使用権を販売するなど、オート・クチュールのメゾンが多角経営化(多角化)しました。
このように、オート・クチュールは衣料品の民衆化によって経営に破綻をきたし、その後プレタ・ポルテ(既製服)その他の部門への進出によって企業体として存続してきました。
従来の先入観では、モードといえばパリ、パリといえばオート・クチュール、オート・クチュールといえばオート・クチュール組合という連想が出てきますが、『モードの物語』を読めば、このような先入観が流行史・衣服史・衣装史の非常に限られた側面しか示さないことがよく分かります(同書の紹介は「モードの物語」をご覧下さい)。
企業多角化の中のアンドレ・クレージュ
オート・クチュール企業の多角化は1960年代に始まりました。
パリのオート・クチュール業界の中でプレタ・ポルテ部門をもっていた4社(ピエール・カルダン、ニナ・リッチ、イヴ・サンローラン、アンドレ・クレージュ)は、オート・クチュールとプレタ・ポルテの2事業を1つにまとめる目的でファッション・ショーのスケジュール変更を協議しました。
サンローランは直ぐに協議から抜けましたが、ピエール・カルダンとニナ・リッチは70年代初頭まで自分のスケジュールを貫きました。
この過程でアンドレ・クレージュは4シリーズを同時に発表しました。ちなみに、1964年にクレージュはフランスのブルジュにあるサミー・エ・モーリス・ヴァンベルグの既製服工場を訪問し、縁縢・笹縁・釦穴に関しては、少なくとも手作業よりミシンの方が遥かに上手に縫製のできる事を知りました。

ポーにあるクレージュのアトリエの様子 (c) Courreges / DR, ディディエ・グランバック『モードの物語―パリ・ブランドはいかにして創られたか―』古賀令子監修、井伊あかり訳、文化出版局、2013年、130頁
アンドレ・クレージュはミシンを直視したからこそ、自らも参加してきたオート・クチュール業界について次のように述べる事ができたのです。
私はよく、こういう質問を受けます。あなたが<プロトタイプ>(原型)と呼んでいるオートクチュールは、必要なのでしょうか…、お客さんはいるのですかと。そこで、私はこう答えるのです。どのような分野に置いても、研究部門を持つことは必要不可欠です。研究の役割は先へ行くことです。たとえ何も変化しないとしても目先の目標など考えずに先へ行くことなのですよと。(ブリュノ・デュ・ロゼル『20世紀モード史』西村愛子訳、平凡社、1995年、471頁)
オート・クチュール組合に対するアンドレ・クレージュの抵抗に関する詳細は「アンドレ・クレージュ : André Courrèges」をご参照ください。





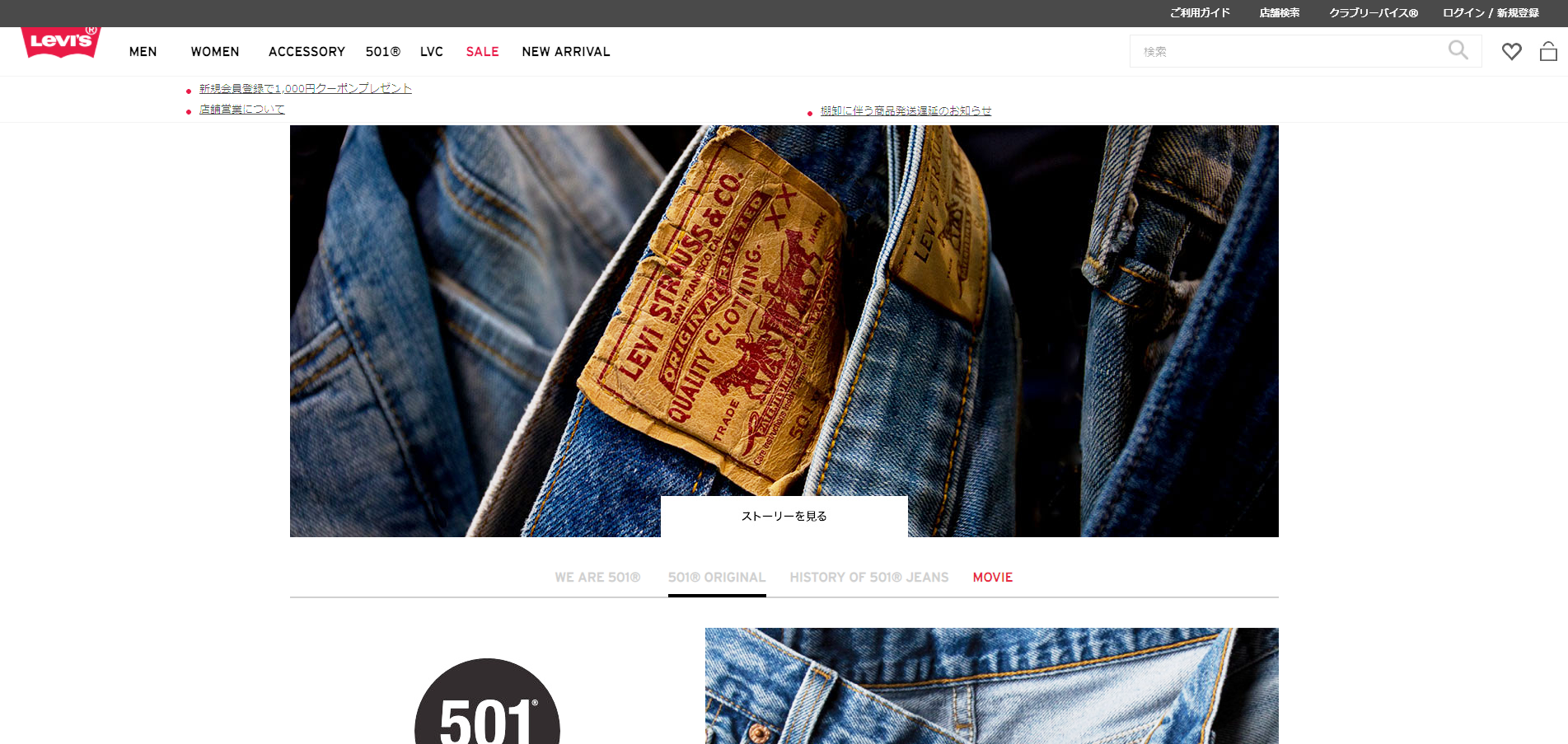
レビュー 作品の感想や女優への思い